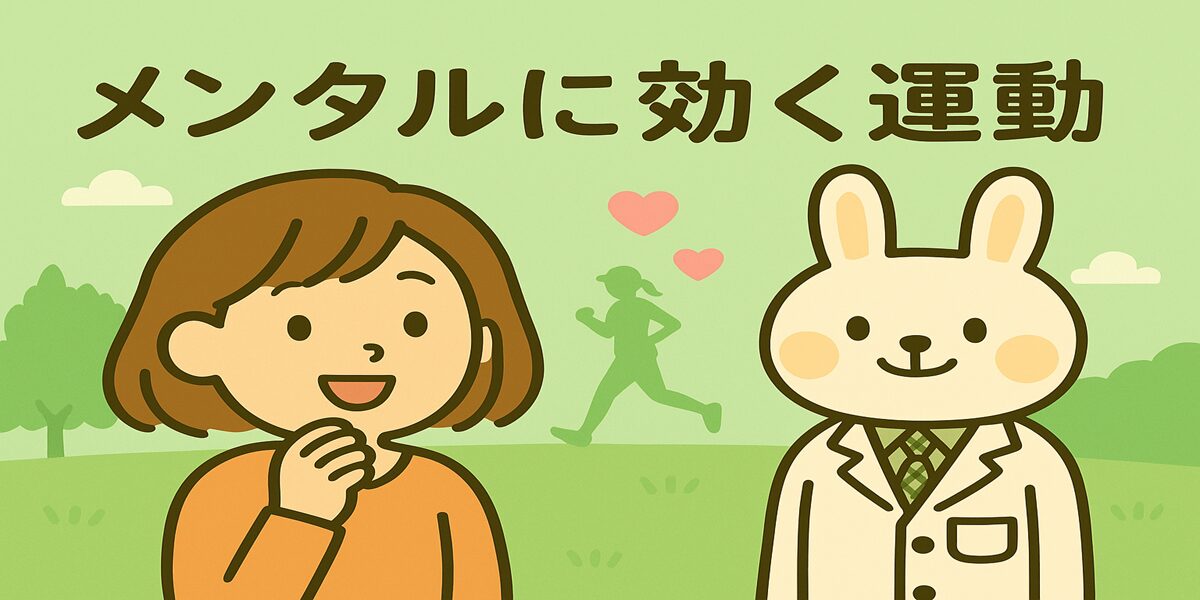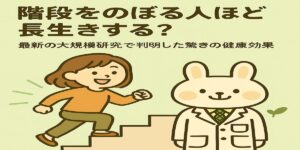「最近なんとなく気分が晴れない」「やる気が出ない」
そんなときに、まず試してみたいのが「運動」です。
ここ数年、心の不調と向き合う方法として運動が注目されています。そして2024年、医学誌『BMJ』に掲載された大規模研究では、運動がうつ病の症状を有意に改善することが明らかになりました(出典)。
 すずちゃん
すずちゃん先生、運動ってほんとにメンタルにも効くんですか?



ええ、2024年のBMJ論文では、ウォーキングや筋トレ、ヨガ、ダンスなどがうつ病の症状を改善するって示されているのよ。



ダンスも効くって…それなら私にもできそうかも!
この記事では、「どんな運動がどんなふうに心に効くのか?」を最新の科学的根拠をもとにやさしく解説します。運動習慣がない人でも安心して読めるよう、無理なく始められる実践ポイントもご紹介します。
※心の不調にはいろいろな要因があります。強い落ち込みや日常生活がつらい状態が続く場合は、まず専門の医療機関にご相談ください。この記事は運動の効果を紹介するもので、治療そのものを代替するものではありません。
✅ この記事でわかること
- 2024年の最新研究が示す「運動とメンタル改善」の驚きの関係
- メンタル改善効果が高いとされたおすすめの運動5つ(ダンス、筋トレ、ヨガなど)
- 運動が脳や神経にどのように作用するのか?(セロトニン・BDNF・コルチゾールなどの関係)
- 自然の中で運動する「グリーンエクササイズ」や、グループでの運動の効果
- 運動を生活に取り入れるための具体的アドバイス(頻度・時間・始めやすさ)
🧪 運動は本当にメンタルに効く?最新研究が示す事実
心の不調に「運動が効く」と言われても、「本当に?」と思う人も多いかもしれません。ですが、その疑問にしっかり答えてくれる科学的な証拠が、2024年に発表されました。
世界的な医学誌『BMJ』に掲載されたネットワークメタ解析では、運動がうつ病の症状を有意に改善することが明らかになったのです(論文リンクはこちら)。
🔍 どんな研究?
- 対象となったのは218件のランダム化比較試験(RCT)と14,170名の参加者
- 解析されたのは、「運動をすると、うつ病の症状がどれくらい改善されるか」
- 比較対象には「薬物治療」「カウンセリング」「ストレッチのみ」などが含まれており、運動単体の効果も評価されています



へぇ〜、そんなにたくさんの研究が集められてたんですね!



そうなの。しかも運動の種類や強度、続けやすさまで評価していて、かなり信頼性の高いデータよ。
📊 主なポイント
- 効果があった運動の種類
ウォーキング・ジョギング、筋トレ、ヨガ、太極拳、ダンスなど
→ なかでもダンスは特に効果が大きいとされましたが、研究数が少ないため信頼度はやや低めと評価されています - 強度と効果の関係
中〜高強度の運動(例:ランニング、筋トレ)は、軽めの運動よりも効果が大きい傾向にありました - 継続しやすい運動は?
筋トレとヨガはドロップアウト率(途中でやめる人の割合)が少ないことから、「続けやすい運動」としても注目されています
🧩 研究の限界と信頼性
この研究は非常に有力なデータを提供していますが、一部の結果には注意が必要です。
- 多くの試験で盲検化(誰がどの治療を受けたか隠す手法)が難しいため、バイアスのリスクがある
- 結果の信頼度は、「ウォーキングやジョギング=低い」「その他の運動=非常に低い」と評価されている
とはいえ、抗うつ薬や認知行動療法と同程度の効果が示されたことは、運動が「補助」ではなく主要な治療選択肢になり得ることを強く示しています。



つまり、“運動=気休め”なんて思わなくていいの。しっかりエビデンスに基づいた“効く方法”として注目されてるのよ。



それなら、ちょっとやってみようかな…
🏃♀️ メンタル改善に効果的!おすすめ運動5選
BMJ論文ではさまざまな運動が検証されましたが、特に効果が高いとされた5つを紹介します。いずれもメンタル改善に有効とされたエビデンスがありますが、信頼度の違いにも注意しながら、自分に合ったものを選ぶのがポイントですBMJ論文(2024)、Prudente et al., 2024。
① ダンス|楽しみながら心も体もリズムに乗せて
- 効果量:Hedges’ g = –0.96(最も大きい効果)
- 95% 信頼区間:–1.36〜–0.56
- 信頼度:非常に低い(研究数5件、参加者107人)
- 特徴:音楽・身体表現・社交性が組み合わさり、感情の解放やストレス発散に効果的



ダンスって、ただ楽しいだけじゃなかったんですね…!



そう。でも研究数がまだ少ないから、これからもっと検証される必要があるのよ。
② 筋力トレーニング|心も強くする“メンタルトレ”の王道
- 効果量:g = –0.49
- 信頼度:非常に低い
- 特徴:自己効力感の向上や体調改善が、メンタル回復を後押し
さらに、脱落率が低く継続しやすいことから「受容性の高い運動」としても評価されています
筋力トレーニングは、派手さはないものの「長期的に信頼できる土台」をつくる運動といえます。
③ ヨガ|呼吸と静かな動きで心をほぐす
- 効果量:g = –0.55
- 信頼度:非常に低い
- 特徴:マインドフルネスや呼吸法を通じて、不安やストレスの軽減に寄与
筋トレと並び、脱落率が低く、継続しやすい点も高評価
ヨガは「心を耕す庭」のように、静かに自己と向き合う時間をつくってくれます。
④ ウォーキング・ジョギング|いつでも誰でもできる王道
- 効果量:g = –0.63
- 信頼度:低い(比較的高評価)
- 特徴:始めやすく、コストゼロ。さらに自然の中で行うと、グリーンエクササイズとしての効果も期待されます



自然の中を歩くだけでも、ちゃんと効くんですね〜



ええ。手軽だけど、効果はばっちりよ。
⑤ 太極拳・気功|やさしい動きでじんわり効く
- 効果量:g = –0.42
- 信頼度:非常に低い
- 特徴:高齢者や体力に不安のある人でも取り組みやすく、穏やかな動きや呼吸を通じて神経系を整える可能性があるとされています



“静”の運動も立派なセルフケアになるのよ。



これなら私の祖母にもすすめられそう!
📝 まとめ:どの運動がベスト?
どの運動もメンタル改善に効果が見られましたが、重要なのは以下の視点です:
- 最大効果量を示したのはダンス(g = –0.96/信頼度は非常に低い)
- 継続しやすさ・脱落率の低さでは筋トレとヨガが優秀
- 始めやすさ・安全性ならウォーキングや太極拳がおすすめ



“効果が高い”だけじゃなく、“自分が続けられるか”が本当に大事なのよ。
🧠 なぜ運動がメンタルに効くの?脳とホルモンのしくみ
「運動するとスッキリする」という経験、あなたにもきっとあるはず。
実はそれ、気のせいではなく、脳と体の“本当の反応”なんです。
2024年のBMJ論文でも、運動がメンタルに効く理由として、神経科学的なメカニズムの存在が示唆されています。ここでは、その代表的なしくみを3つに絞って紹介します。
① セロトニン・ドーパミン|気分を上げる脳内物質が増える
運動によって分泌が促進される脳内物質の代表格が「セロトニン」や「ドーパミン」です。
- セロトニン:心の安定や睡眠、食欲などを調整する神経伝達物質。「幸福ホルモン」とも呼ばれます
- ドーパミン:やる気や快感に関与する物質。報酬系の働きを活性化し、「やってよかった感」を高めます



“幸せホルモン”ってほんとにあるんだ…!



ええ。特にウォーキングや軽い有酸素運動は、セロトニン分泌を穏やかに高めてくれるわよ。
② BDNF(脳由来神経栄養因子)|脳そのものを“育てる”
- BDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor)は、脳の可塑性(柔軟さ)や神経の修復・再生に関わる重要なタンパク質
- 運動によってこのBDNFが増えると、海馬(記憶や感情を司る領域)の機能が改善し、うつ病の回復にも貢献すると考えられています。Pahlavani et al., 2024



運動で脳が元気になるって、ちょっとすごい話ですね!



“心の調子”は“脳の健康”と直結してるの。だからBDNFの存在はとても大切なのよ。
③ コルチゾール(ストレスホルモン)|過剰なストレス反応を抑える
- ストレスが続くと、コルチゾールというホルモンが分泌され、気分の落ち込み・疲労・睡眠障害などの原因に
- 運動はこのコルチゾールの分泌を適切なレベルに調整し、ストレス過多の状態から心を守ってくれます
さらに、軽度〜中程度の運動を自然の中(緑地)で行うと、より高いストレス緩和効果があるとされています(グリーンエクササイズ)Gladwell et al., 2013
💡 その他のしくみ
研究者たちは、他にも運動によるメンタル改善のしくみとして以下を挙げています:
- 自己効力感の向上:「自分で自分をケアできた」という成功体験が自信につながる
- マインドフルネス効果:特にヨガや太極拳では「今ここ」に意識を向ける習慣が反芻(くよくよ思考)を減らす
- 社会的つながり:グループ運動は「孤立感の軽減」に役立つ



“運動=汗をかくだけ”じゃなくて、ちゃんと“脳にも効く”ってわかると、やる意味が深まるわよね。



体と心って、やっぱりつながってるんですね〜!
💪 効果を最大限引き出すための“運動のコツ”|頻度・強度・続け方
運動がメンタルに効くことは研究で明らかになっていますが、
「どれくらいやればいいの?」
「どんなやり方が続けやすいの?」
と疑問に思う方も多いはず。
ここでは、無理なく・安全に・確実に効果を高める方法をお伝えします。
① まずは“週2〜3回・30分”を目安に
BMJ論文が示すデータや、多くのメタ解析を総合すると、
- 中程度の運動:1回20〜45分
- 週2〜3回以上
このあたりからメンタル改善効果が見られやすくなります。
「毎日やらなきゃ!」と思わなくて大丈夫。
研究でも、継続できる頻度でコツコツが最も効果的だとされています。



最初から完璧を目指すより、“週2回のゆるい運動”を続けるほうがメンタルにも良いのよ。



私でもいけそうかも…!
② 強度は“軽〜中程度”でOK(慣れたら少しずつ)
BMJ論文では、強度が高い運動ほど効果量が大きい傾向がみられました。
とはいえ初めから無理は禁物。
運動初心者は…
- 息が少し上がるくらい(軽〜中強度)
- 会話がぎりぎりできる程度
から始めてみましょう。
慣れてきたら、徐々に強度を上げていくことで、
セロトニン・BDNF・ドーパミン分泌がより高まりやすくなります。
③ “続けやすい運動”を選ぶことが実は最重要
どんな運動でも、続かなければ効果は限定的になってしまいます。
BMJ論文でも、途中離脱(ドロップアウト)率の低い運動ほど受容性が高いと結論づけています。
脱落率が低かった運動は…
- 筋力トレーニング(非常に継続しやすい)
- ヨガ(最も継続しやすい運動の一つ)
逆に、ダンスは効果量は大きいですが、研究数が少なくバイアスリスクも高いため、「誰にでも続けやすいか」はまだ要検証です。



続けられるかどうかって、やっぱり大事なんですね。



そうよ。続けやすさは立派な“治療効果の一部”なの。
④ グループで行うと効果が高まりやすい
研究では、グループ運動や誰かと一緒に行う運動は継続率が高いと報告されています。
- 社会的サポート
- 会話や交流による孤立感の改善
- “一緒にやる”ことで自己効力感が高まりやすい
こうした心理的効果が、メンタル改善にもプラスに働きます。



友だちと一緒なら続けられそう!



そうね。オンラインで一緒にやるのも立派なグループ効果よ。
⑤ 自然の中で運動すると“追加のご褒美効果”
グリーンエクササイズ研究では、
自然環境(公園・川沿い・森)でのウォーキングは、室内よりストレス軽減効果が高いことが示されています。
(Gladwell et al., 2013)
- 視覚的な癒し
- 騒音の少なさ
- 自律神経の安定
- 気分の落ち着き
こうした効果が、通常の運動に“上乗せ”されます。
⑥ まずは「できる範囲」で、短時間からで十分
最も避けたいのは “頑張りすぎて嫌になること”。
うつ状態やストレス過多のときは、そもそも動き出すエネルギーが不足しています。
- 3分だけストレッチ
- 家の周りをひと回り歩く
- ラジオ体操をひとつやる
- ヨガのポーズを一つだけ
こんな小さな活動でも、脳は“行動した”ことをポジティブに受け止めます。



“0分→3分”の差はすごく大きいのよ。



えっ、たった3分でも?それならできそう!
⑦ 自分に優しく。調子の波があってOK
メンタルと運動の関係は“線形”ではなく、“波”があります。
- 調子が良い日 → 少し長めに
- しんどい日 → 足踏み運動だけ、深呼吸だけ
これで大丈夫。
大事なのは「やめないこと」であって、「完璧にこなすこと」ではありません。
🌱 まとめ:運動は“心のリハビリ”。小さな一歩を積み重ねよう
- 週2〜3回、短時間からでOK
- 強度は軽〜中から
- 続けやすい運動(筋トレ・ヨガ・ウォーキング)がおすすめ
- グループ効果・自然の力も取り入れるとさらに◎
- 調子の波があってもOK。やめなければ前に進める



運動は“心のリハビリ”にもなるの。できることを少しずつね。



今日、帰りに公園を少し歩いてみようかな!
🧩 まとめ:運動は「心の回復力」を育てるいちばん身近な方法
2024年のBMJ大規模研究でも確認されたように、
運動はうつ病の症状を改善できる、エビデンスに基づいた確かな選択肢です。
- ダンスは大きな効果量
- 筋トレとヨガは続けやすく、自己効力感も高めやすい
- ウォーキングや太極拳は手軽で、体力に自信がなくても安心
- 自然や人とのつながりを組み合わせれば、さらに効果を高められる
こうした研究結果を総合すると、運動が心に効く理由はとてもシンプルです。
「動くことで、脳と自律神経が整い、心の回復力(レジリエンス)が育つから」。
🌱 今日からできる、小さな一歩。
運動は“努力”ではなく、“セルフケア”です。
うつ症状や気分の落ち込みで体が重くなる日は、誰にだってあります。



私、なんだか動くの苦手で…。



大丈夫。たとえば“3分だけ歩く”でも、脳はしっかり前向きに反応するのよ。
- 3分ストレッチ
- 家の周りを少し歩く
- ラジオ体操ひとつ
- 深い呼吸を数回
こうした小さな行動でも、脳は確実に変わっていきます。
🌈 運動を続けた先に見える未来
運動を小さく積み重ねていくと…
- 朝のだるさが少し軽くなる
- 気分の落ち込みに引きずられにくくなる
- 「自分でもできた」という自信が芽生える
- 気持ちが安定し、日常にメリハリが戻ってくる
そんな未来が、自然に見えてきます。



今日の小さな一歩が、未来のあなたの力になるの。



まずは帰り道を5分だけ遠回りして歩いてみます!
運動は特別な道具もスキルもいりません。
あなたのペースで、今日できる“ほんの少しの動き”からで大丈夫。
この記事が、あなたの“心を整える習慣づくり”のきっかけになれたら嬉しいです。
📝 ご注意ください
・本記事は、信頼できる資料をもとに薬剤師が分かりやすくまとめた一般情報です。
・内容には十分配慮していますが、個別の症状や体質には必ず医師・薬剤師へご相談ください。
・万一誤り等にお気づきの際は、そっとご指摘いただけると幸いです。
参考文献
- Noetel, M., Sanders, T., Gallardo-Gómez, D., et al.
Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 2024;384:e075847.
https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-075847 - Prudente, T. P., Santana, C. D., de Oliveira, E. V., et al.
Effect of Dancing Interventions on Depression and Anxiety Symptoms in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clinical Interventions in Aging, 2024;19:171-187.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10813489/ - Pahlavani, H. A., Eftekhari, M. H., Asbaghi, O., et al.
Possible role of exercise therapy on depression: Effector neurotransmitters as key players. Neuroscience Research, 2024;194:22-35.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166432823005090 - Gladwell, V. F., Brown, D. K., Wood, C., et al.
The great outdoors: how a green exercise environment can benefit all. Extreme Physiology & Medicine, 2013;2:3.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3710158/